 写真は、「さぬき富士もゲストハウス」基本設計時に使用したstudy模型です。計20種類ぐらいの四角いBOXを用意しておいた上で、施主に時間を割いて貰い、一緒に、ちょっとづつ動かしたり、回したり…。下の敷地をかたどったスチレンボードに何パターンもチェックしていきます。
写真は、「さぬき富士もゲストハウス」基本設計時に使用したstudy模型です。計20種類ぐらいの四角いBOXを用意しておいた上で、施主に時間を割いて貰い、一緒に、ちょっとづつ動かしたり、回したり…。下の敷地をかたどったスチレンボードに何パターンもチェックしていきます。親戚や親しい友人と集うゲストハウスがゆえ、BOXの配置を検討、決定していく過程において、同時に、人と人の向かい合い方、家族同士の距離感、そして、敷地外部のさぬき富士との関わり方までも感覚の中にある、また、逆に感覚の中にしかないものも全員が無意識に意識する、そんな場になったような気がしております。
決定に至ったこの配置は、見えない何かが表現されていることでしょう。
 実施設計は、これをそのままSCANしてCADに落とし込んで図面にしていきました。
実施設計は、これをそのままSCANしてCADに落とし込んで図面にしていきました。フォルムを施主と共に決めていくことで、逆に、僕には出来ない建築に行き着いているのかもしれません。
,
この物件を通し、ふと振り返ると、事務所を開設して、早6年。最初は自分の出来ることの枠を広げよう、広げよう、としてきた意識が大半であったような気がしてます。だからこそ出来たことも多い。もちろん自分の中にある経験や本質の中にあるものを再認識、再定義を繰り返した中で「普遍的である新しさ」と言うものを模索したいという思いは今も変わりませんが。しかし現在は、どちらかと言えば、出来ることを疑い、狭めていこう、という意識も強くなってきていることも感じています。あえて良い様に表現すれば、自分に対しても施主に対しても、より地に足の付いたものと言うか…。本当にやるべきこととは何なのかということの選択。そういう過程がひめられたもの。
、
この2者、どちらかだけでも駄目なのでしょうが、ただ、これに恐らく中間点など無く、ただ繰り返していくべきことだろうとも感じています。
挑戦(チャレンジ)・「自分にとっても新しいか」という言葉や問いは、大事な事ではありますが、本来はこれを何度も繰り返して、繰り返して、始めて力ある行為になるのではないかと。 …まだまだ先か。
、
建築家・隈研吾の著書に「負ける建築」という本があります。本を読んでいないので申し訳ないが、その本意は分かりませんが、言葉として大事な忘れてはいけないことが多く詰まった一言。
、
結果、本物件「さぬき富士もゲストハウス」は、施主に導いて貰った建築でもあります。
状況や施主に委ねることで生まれることもあり、それを柔軟に理解していくことも挑戦なのかなと。
基本設計の過程は特殊な方法ではありますが、問いに対し新鮮な気持ちで向き合えた物件なのかなと思う次第です。 長田
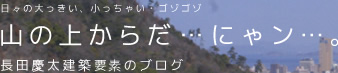
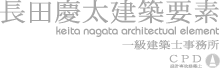






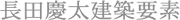
0 コメント::
コメントを投稿