TVなどのマスメディアなどからは、伝わってきませんが、「東日本大震災」の応急仮設住宅の中にこういう物があります。先月の「建築士会の会報」にて。
遠野市の例:

 中庭には、入居者たちの畑が作られるらしい。
中庭には、入居者たちの畑が作られるらしい。いわき市の例:

 住宅造成地の再利用。
住宅造成地の再利用。背景として・・・
今までは、地震の規模・範囲もあり、プレハブメーカーが一手に担ってきたが、今回の震災は甚大かつ広範囲であった。しかも、既設工法に必要な合板・ボード・グラスウール断熱材等の不足もあり、プレハブだけでの対応が困難な状況を生んだ。国の県寄りの復興策も相まり、地元業者に一部発注された経緯がある。
そこに大学教授や建築家が手を差し伸べることで日本独特の新たな形が生まれている。
杉材の断熱性・調湿性
ススキ・籾がら、を断熱材として利用する等
建材不足への対応と現地調達も行われている。
その上、復興後の解体や処分にかかる莫大な処理費用を抑えるべく、復興住宅としての利用をも想定。
すばらしいのは、この全体を見据えた大きな繋がりを短期間に持ち込めているという、元々「持ち合わせた」だろう思想・技量。

地図を見て頂くと、多くは決してないが、少ないわけでもないのは把握して頂けるでしょう。
 建築や空間・・・そして、人同士の繋がり・・・外部環境との連動が、人を人として成り立たせる大きな要因になり得ることを見せてくれます。
建築や空間・・・そして、人同士の繋がり・・・外部環境との連動が、人を人として成り立たせる大きな要因になり得ることを見せてくれます。「豊か」だから生まれる建築の形、「乏しい」から必要とされる建築の形。
本来そこに大きな差があってはいけないのだろう。
建築家自身も自らと社会の接点を再度捉え直し、これからを進んで行くべきであろう。 長田
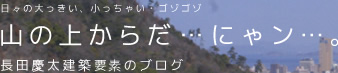
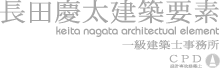






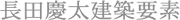
0 コメント::
コメントを投稿